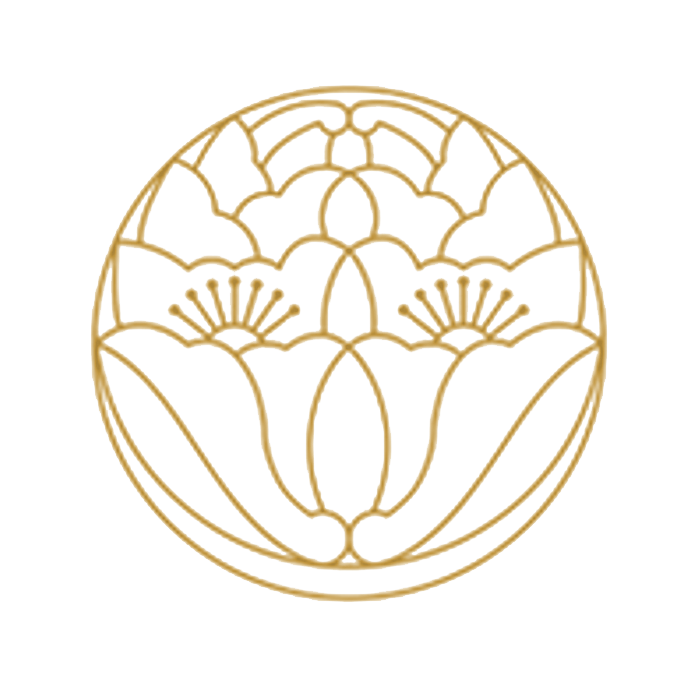「聖冏」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
Seishimaru (トーク | 投稿記録) 細 (1版 をインポートしました) |
Seishimaru (トーク | 投稿記録) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
=しょうげい/聖冏= | =しょうげい/聖冏= | ||
| − | 暦応四年(一三四一)一〇月一五日—応永二七年(一四二〇)九月二七日。<ruby>酉[[蓮社]]<rt>ゆうれんじゃ</rt></ruby>了誉。[[浄土宗]][[七祖]]。[[小石川]][[伝通院]][[開山]]。常陸国久慈郡岩瀬(茨城県常陸大宮市)の人。父は同国岩瀬の城主白石志摩守[[宗義]](一説に義光という)で佐竹氏の一族であった。この頃天下は南北朝にわかれて争う戦乱の世であり、父はその合戦中に討死した。八歳のとき<ruby>[[瓜連]]<rt>うりづら</rt></ruby>[[常福寺]][[了実]]について[[出家]][[剃髪]]し、[[聖冏]]という名を与えられた。一五歳で常陸太田の[[蓮勝]]に学び、一八歳で[[箕田]]の[[浄土宗]]五祖[[定慧]]について[[浄土宗]]義の指南を受けた。[[浄土]]の経論、教相行儀はもちろん、『[[起信論]]』『釈[[摩訶衍]]論』など一般[[仏教]]や各宗の章疏にわたった。二五歳で[[定慧]]より[[二祖三代]]の[[宗義]][[行業]]ならびに[[円頓]]、[[布薩]]の大戒などの全てにわたって伝えられた。このように[[聖冏]]は[[宗義]]の真髄に達したが、当時の[[浄土宗]]勢の実際は、禅僧[[虎関師錬]]が『[[元亨釈書]]』の中で<ruby>[[寓宗]]<rt>ぐうしゅう</rt></ruby>、<ruby>附庸宗<rt>ふようしゅう</rt></ruby>と呼んだような、また天龍寺の[[夢窓疎石]]が『夢中[[問答]]』の中で[[浄土宗]]は小乗であって大乗ではないといったような批判を受けて、故意に低く受けとられる傾向があった。これを嘆いた[[聖冏]]は愛宗護法の念に燃えて、さらに諸宗諸学を学び切磋琢磨の功をつむべきであるとし、各宗の碩学を歴訪し、天台を[[真源]]に、[[真言]]を宥尊に、俱舎[[唯識]]を明哲に、禅を月庵と天命に、[[神道]]を治部大輔某に、[[和歌]]を[[頓阿]]に学んだ。著書や[[説法]]も、多くは対外的ないわゆる随他扶宗の立場をとり、しかもその論陣は雄壮で、その言葉も鋭利で、諸[[宗学]]者から注目をあびた。その結果、各宗に対する[[浄土宗]]の地位があがり、退嬰的な風潮を転換させた功績は大きく、[[後世]][[檀林]]教学の教科書として[[聖冏]]の「<ruby>[[頌義]]<rt>じゅぎ</rt></ruby>」が必要不可欠のものとなった。「[[頌義]]」とは『[[釈浄土二蔵義]]』三〇巻と『[[浄土二蔵二教略頌]]』一巻をいい、[[浄土宗]]が諸宗超過の法門であることを示している。そのほか、対外的なものとしては『[[破邪顕正義]]』一巻があり、これは『鹿島[[問答]]』ともよばれ、[[本地垂迹]]説のほか、[[日蓮宗]]の反[[念仏]]論を破斥し、[[禅宗]]の夢窓の[[浄土]]小乗論を論破し、生即[[無生]]、[[他力]]実体の深義などを述べたものである。一方[[祖師]]の書を詳しく祖述顕彰した力作として『<ruby>[[糅鈔]]<rt>にゅうしょう</rt></ruby>』四八巻、『<ruby>[[直牒]]<rt>じきてつ</rt></ruby>』一〇巻がある。[[聖冏]]の功績中大なるものは、[[伝法]]制度の確立である。これまで[[浄土宗]]には立派な[[道場]]は少なく、また[[宗徒]]の養成も統一あるものではなかった。そこに他宗から独立の宗派とみなされない理由があったので、[[聖冏]]はまず『[[浄土真宗付法伝]]』一巻を書き、[[浄土宗]]には[[釈尊]]以来[[師資相承]]の[[譜脈]]のあることをあらわし、また『[[顕浄土伝戒論]]』では、[[浄土宗]]は[[慈覚大師]]正流の[[円頓戒]]を[[相伝]]していることを力説した。このように宗脈と[[戒脈]]の[[伝灯]][[相承]]のあることを明らかにすると共に、一宗の僧となるためには、必ず[[宗戒両脈]]を[[相伝]]しなければならないと規定して、[[宗徒]]養成の確固たる基礎を築いた。[[聖冏]]が主唱した伝宗は、いわゆる[[五重相伝]]の法であって、[[法然]]作と伝える『[[往生記]]』(初重)、[[聖光]]の『[[授手印]]』(二重)、[[良忠]]の『[[領解抄]]』(三重)、[[良忠]]の『[[疑問抄]]』(四重)、[[曇鸞]]の凝思[[十念]]伝(五重)の[[次第]]をたてて、機・法・解・証・信の綱格にのっとって[[宗義]]を[[相承]]して[[血脈]]を伝授することをいう。[[聖冏]]は五重の内容をさらに明確にするため、『[[投機抄]]』『[[徹心抄]]』『[[銘心抄]]』『[[伝心抄]]』をあらわし、ここにはじめて<ruby>三巻<rt>さんがん</rt></ruby>(『[[往生記]]』『[[授手印]]』『[[領解抄]]』各一巻)<ruby>七書<rt>しちしょ</rt></ruby>(『[[疑問抄]]』二巻、『[[投機抄]]』一巻、『[[伝心抄]]』一巻、『[[徹心抄]]』一巻、『[[銘心抄]]』二巻)が整った。明徳四年(一三九三)一二月にこれらを五重に分かち、それぞれその[[血脈]]を整え、これに口訣をそえて儀式を定め、[[弟子]][[聖聡]]に授与した。これが五重[[伝法]]の始まりといわれ、この五重の制定によって一宗の[[僧侶]]を同[[一形]]式によって統一して養成することができた。こうして[[浄土宗]]は名実共に独立[[教団]]となって[[後世]]発展の基礎が確立した。それと共に五重[[伝法]]の行儀は[[後世]]在家の者に[[安心]]決定させる<ruby>捷径<rt>しょうけい</rt></ruby>を開いたのである。また応永一一年(一四〇四)には[[三巻七書]]のそれぞれについての[[口伝]]を記し、合わせて五五箇条の『[[五重指南目録]]』一巻を作った。同二二年八月[[聖聡]]の請により、<ruby>[[瓜連]]<rt>うりづら</rt></ruby>[[常福寺]]を[[弟子]]了智に譲り、江戸[[小石川]]に移り[[草庵]]にいること六年、[[自行化他]]に励んだが、病をえて八〇歳をもって寂した。この[[草庵]]が後の[[無量]]山[[伝通院]]寿経寺である。著書は前記のほかに『二蔵二教[[見聞]]』『[[往生礼讃見聞]]』『[[浄土略名目図]]』『[[浄土略名目図見聞]]』『[[教相十八通]]』『[[三六通裏書]]』『[[心具決定往生義]]』『[[観心要決集]]』『[[一枚起請文]]註解』『不思議鈔』『[[隼疑冏決集]]』『[[勧心往生論]]慈訓仏鈔』『[[仏像標幟義]] | + | 暦応四年(一三四一)一〇月一五日—応永二七年(一四二〇)九月二七日。<ruby>酉[[蓮社]]<rt>ゆうれんじゃ</rt></ruby>了誉。[[浄土宗]][[七祖]]。[[小石川]][[伝通院]][[開山]]。常陸国久慈郡岩瀬(茨城県常陸大宮市)の人。父は同国岩瀬の城主白石志摩守[[宗義]](一説に義光という)で佐竹氏の一族であった。この頃天下は南北朝にわかれて争う戦乱の世であり、父はその合戦中に討死した。八歳のとき<ruby>[[瓜連]]<rt>うりづら</rt></ruby>[[常福寺]][[了実]]について[[出家]][[剃髪]]し、[[聖冏]]という名を与えられた。一五歳で常陸太田の[[蓮勝]]に学び、一八歳で[[箕田]]の[[浄土宗]]五祖[[定慧]]について[[浄土宗]]義の指南を受けた。[[浄土]]の経論、教相行儀はもちろん、『[[起信論]]』『釈[[摩訶衍]]論』など一般[[仏教]]や各宗の章疏にわたった。二五歳で[[定慧]]より[[二祖三代]]の[[宗義]][[行業]]ならびに[[円頓]]、[[布薩]]の大戒などの全てにわたって伝えられた。このように[[聖冏]]は[[宗義]]の真髄に達したが、当時の[[浄土宗]]勢の実際は、禅僧[[虎関師錬]]が『[[元亨釈書]]』の中で<ruby>[[寓宗]]<rt>ぐうしゅう</rt></ruby>、<ruby>附庸宗<rt>ふようしゅう</rt></ruby>と呼んだような、また天龍寺の[[夢窓疎石]]が『夢中[[問答]]』の中で[[浄土宗]]は小乗であって大乗ではないといったような批判を受けて、故意に低く受けとられる傾向があった。これを嘆いた[[聖冏]]は愛宗護法の念に燃えて、さらに諸宗諸学を学び切磋琢磨の功をつむべきであるとし、各宗の碩学を歴訪し、天台を[[真源]]に、[[真言]]を宥尊に、俱舎[[唯識]]を明哲に、禅を月庵と天命に、[[神道]]を治部大輔某に、[[和歌]]を[[頓阿]]に学んだ。著書や[[説法]]も、多くは対外的ないわゆる随他扶宗の立場をとり、しかもその論陣は雄壮で、その言葉も鋭利で、諸[[宗学]]者から注目をあびた。その結果、各宗に対する[[浄土宗]]の地位があがり、退嬰的な風潮を転換させた功績は大きく、[[後世]][[檀林]]教学の教科書として[[聖冏]]の「<ruby>[[頌義]]<rt>じゅぎ</rt></ruby>」が必要不可欠のものとなった。「[[頌義]]」とは『[[釈浄土二蔵義]]』三〇巻と『[[浄土二蔵二教略頌]]』一巻をいい、[[浄土宗]]が諸宗超過の法門であることを示している。そのほか、対外的なものとしては『[[破邪顕正義]]』一巻があり、これは『鹿島[[問答]]』ともよばれ、[[本地垂迹]]説のほか、[[日蓮宗]]の反[[念仏]]論を破斥し、[[禅宗]]の夢窓の[[浄土]]小乗論を論破し、生即[[無生]]、[[他力]]実体の深義などを述べたものである。一方[[祖師]]の書を詳しく祖述顕彰した力作として『<ruby>[[糅鈔]]<rt>にゅうしょう</rt></ruby>』四八巻、『<ruby>[[直牒]]<rt>じきてつ</rt></ruby>』一〇巻がある。[[聖冏]]の功績中大なるものは、[[伝法]]制度の確立である。これまで[[浄土宗]]には立派な[[道場]]は少なく、また[[宗徒]]の養成も統一あるものではなかった。そこに他宗から独立の宗派とみなされない理由があったので、[[聖冏]]はまず『[[浄土真宗付法伝]]』一巻を書き、[[浄土宗]]には[[釈尊]]以来[[師資相承]]の[[譜脈]]のあることをあらわし、また『[[顕浄土伝戒論]]』では、[[浄土宗]]は[[慈覚大師]]正流の[[円頓戒]]を[[相伝]]していることを力説した。このように宗脈と[[戒脈]]の[[伝灯]][[相承]]のあることを明らかにすると共に、一宗の僧となるためには、必ず[[宗戒両脈]]を[[相伝]]しなければならないと規定して、[[宗徒]]養成の確固たる基礎を築いた。[[聖冏]]が主唱した伝宗は、いわゆる[[五重相伝]]の法であって、[[法然]]作と伝える『[[往生記]]』(初重)、[[聖光]]の『[[授手印]]』(二重)、[[良忠]]の『[[領解抄]]』(三重)、[[良忠]]の『[[疑問抄]]』(四重)、[[曇鸞]]の凝思[[十念]]伝(五重)の[[次第]]をたてて、機・法・解・証・信の綱格にのっとって[[宗義]]を[[相承]]して[[血脈]]を伝授することをいう。[[聖冏]]は五重の内容をさらに明確にするため、『[[投機抄]]』『[[徹心抄]]』『[[銘心抄]]』『[[伝心抄]]』をあらわし、ここにはじめて<ruby>三巻<rt>さんがん</rt></ruby>(『[[往生記]]』『[[授手印]]』『[[領解抄]]』各一巻)<ruby>七書<rt>しちしょ</rt></ruby>(『[[疑問抄]]』二巻、『[[投機抄]]』一巻、『[[伝心抄]]』一巻、『[[徹心抄]]』一巻、『[[銘心抄]]』二巻)が整った。明徳四年(一三九三)一二月にこれらを五重に分かち、それぞれその[[血脈]]を整え、これに口訣をそえて儀式を定め、[[弟子]][[聖聡]]に授与した。これが五重[[伝法]]の始まりといわれ、この五重の制定によって一宗の[[僧侶]]を同[[一形]]式によって統一して養成することができた。こうして[[浄土宗]]は名実共に独立[[教団]]となって[[後世]]発展の基礎が確立した。それと共に五重[[伝法]]の行儀は[[後世]]在家の者に[[安心]]決定させる<ruby>捷径<rt>しょうけい</rt></ruby>を開いたのである。また応永一一年(一四〇四)には[[三巻七書]]のそれぞれについての[[口伝]]を記し、合わせて五五箇条の『[[五重指南目録]]』一巻を作った。同二二年八月[[聖聡]]の請により、<ruby>[[瓜連]]<rt>うりづら</rt></ruby>[[常福寺]]を[[弟子]]了智に譲り、江戸[[小石川]]に移り[[草庵]]にいること六年、[[自行化他]]に励んだが、病をえて八〇歳をもって寂した。この[[草庵]]が後の[[無量]]山[[伝通院]]寿経寺である。著書は前記のほかに『二蔵二教[[見聞]]』『[[往生礼讃見聞]]』『[[浄土略名目図]]』『[[浄土略名目図見聞]]』『[[教相十八通]]』『[[三六通裏書]]』『[[心具決定往生義]]』『[[観心要決集]]』『[[一枚起請文]]註解』『不思議鈔』『[[隼疑冏決集]]』『[[勧心往生論]]慈訓仏鈔』『[[仏像標幟義]]』『報恩謝徳鈔』『述聞口決鈔』『[[涇渭分流集]]』『古今集序註』『天地麗気記鈔』などがある。 |
---- | ---- | ||
【資料】『了誉上人行業記』『鎮流祖伝』(共に浄全一七)、『聖冏禅師絵詞伝』、『東国高僧伝』一〇(仏全一〇四)、『総系譜』中、『小石川伝通院志』、『三縁山志』四(以上、浄全一九)、『本朝高僧伝』一七(仏全一〇二) | 【資料】『了誉上人行業記』『鎮流祖伝』(共に浄全一七)、『聖冏禅師絵詞伝』、『東国高僧伝』一〇(仏全一〇四)、『総系譜』中、『小石川伝通院志』、『三縁山志』四(以上、浄全一九)、『本朝高僧伝』一七(仏全一〇二) | ||
2025年7月11日 (金) 06:29時点における最新版
しょうげい/聖冏
暦応四年(一三四一)一〇月一五日—応永二七年(一四二〇)九月二七日。酉蓮社了誉。浄土宗七祖。小石川伝通院開山。常陸国久慈郡岩瀬(茨城県常陸大宮市)の人。父は同国岩瀬の城主白石志摩守宗義(一説に義光という)で佐竹氏の一族であった。この頃天下は南北朝にわかれて争う戦乱の世であり、父はその合戦中に討死した。八歳のとき瓜連常福寺了実について出家剃髪し、聖冏という名を与えられた。一五歳で常陸太田の蓮勝に学び、一八歳で箕田の浄土宗五祖定慧について浄土宗義の指南を受けた。浄土の経論、教相行儀はもちろん、『起信論』『釈摩訶衍論』など一般仏教や各宗の章疏にわたった。二五歳で定慧より二祖三代の宗義行業ならびに円頓、布薩の大戒などの全てにわたって伝えられた。このように聖冏は宗義の真髄に達したが、当時の浄土宗勢の実際は、禅僧虎関師錬が『元亨釈書』の中で寓宗、附庸宗と呼んだような、また天龍寺の夢窓疎石が『夢中問答』の中で浄土宗は小乗であって大乗ではないといったような批判を受けて、故意に低く受けとられる傾向があった。これを嘆いた聖冏は愛宗護法の念に燃えて、さらに諸宗諸学を学び切磋琢磨の功をつむべきであるとし、各宗の碩学を歴訪し、天台を真源に、真言を宥尊に、俱舎唯識を明哲に、禅を月庵と天命に、神道を治部大輔某に、和歌を頓阿に学んだ。著書や説法も、多くは対外的ないわゆる随他扶宗の立場をとり、しかもその論陣は雄壮で、その言葉も鋭利で、諸宗学者から注目をあびた。その結果、各宗に対する浄土宗の地位があがり、退嬰的な風潮を転換させた功績は大きく、後世檀林教学の教科書として聖冏の「頌義」が必要不可欠のものとなった。「頌義」とは『釈浄土二蔵義』三〇巻と『浄土二蔵二教略頌』一巻をいい、浄土宗が諸宗超過の法門であることを示している。そのほか、対外的なものとしては『破邪顕正義』一巻があり、これは『鹿島問答』ともよばれ、本地垂迹説のほか、日蓮宗の反念仏論を破斥し、禅宗の夢窓の浄土小乗論を論破し、生即無生、他力実体の深義などを述べたものである。一方祖師の書を詳しく祖述顕彰した力作として『糅鈔』四八巻、『直牒』一〇巻がある。聖冏の功績中大なるものは、伝法制度の確立である。これまで浄土宗には立派な道場は少なく、また宗徒の養成も統一あるものではなかった。そこに他宗から独立の宗派とみなされない理由があったので、聖冏はまず『浄土真宗付法伝』一巻を書き、浄土宗には釈尊以来師資相承の譜脈のあることをあらわし、また『顕浄土伝戒論』では、浄土宗は慈覚大師正流の円頓戒を相伝していることを力説した。このように宗脈と戒脈の伝灯相承のあることを明らかにすると共に、一宗の僧となるためには、必ず宗戒両脈を相伝しなければならないと規定して、宗徒養成の確固たる基礎を築いた。聖冏が主唱した伝宗は、いわゆる五重相伝の法であって、法然作と伝える『往生記』(初重)、聖光の『授手印』(二重)、良忠の『領解抄』(三重)、良忠の『疑問抄』(四重)、曇鸞の凝思十念伝(五重)の次第をたてて、機・法・解・証・信の綱格にのっとって宗義を相承して血脈を伝授することをいう。聖冏は五重の内容をさらに明確にするため、『投機抄』『徹心抄』『銘心抄』『伝心抄』をあらわし、ここにはじめて三巻(『往生記』『授手印』『領解抄』各一巻)七書(『疑問抄』二巻、『投機抄』一巻、『伝心抄』一巻、『徹心抄』一巻、『銘心抄』二巻)が整った。明徳四年(一三九三)一二月にこれらを五重に分かち、それぞれその血脈を整え、これに口訣をそえて儀式を定め、弟子聖聡に授与した。これが五重伝法の始まりといわれ、この五重の制定によって一宗の僧侶を同一形式によって統一して養成することができた。こうして浄土宗は名実共に独立教団となって後世発展の基礎が確立した。それと共に五重伝法の行儀は後世在家の者に安心決定させる捷径を開いたのである。また応永一一年(一四〇四)には三巻七書のそれぞれについての口伝を記し、合わせて五五箇条の『五重指南目録』一巻を作った。同二二年八月聖聡の請により、瓜連常福寺を弟子了智に譲り、江戸小石川に移り草庵にいること六年、自行化他に励んだが、病をえて八〇歳をもって寂した。この草庵が後の無量山伝通院寿経寺である。著書は前記のほかに『二蔵二教見聞』『往生礼讃見聞』『浄土略名目図』『浄土略名目図見聞』『教相十八通』『三六通裏書』『心具決定往生義』『観心要決集』『一枚起請文註解』『不思議鈔』『隼疑冏決集』『勧心往生論慈訓仏鈔』『仏像標幟義』『報恩謝徳鈔』『述聞口決鈔』『涇渭分流集』『古今集序註』『天地麗気記鈔』などがある。
【資料】『了誉上人行業記』『鎮流祖伝』(共に浄全一七)、『聖冏禅師絵詞伝』、『東国高僧伝』一〇(仏全一〇四)、『総系譜』中、『小石川伝通院志』、『三縁山志』四(以上、浄全一九)、『本朝高僧伝』一七(仏全一〇二)
【参考】恵谷隆戒『概説浄土宗史』(隆文館、一九七八)、「了誉聖冏上人特集」一(『仏教文化研究』三九、浄土宗教学院、一九九四)、鈴木英之『中世学僧と神道』(勉誠出版、二〇一二)
【執筆者:宇高良哲】