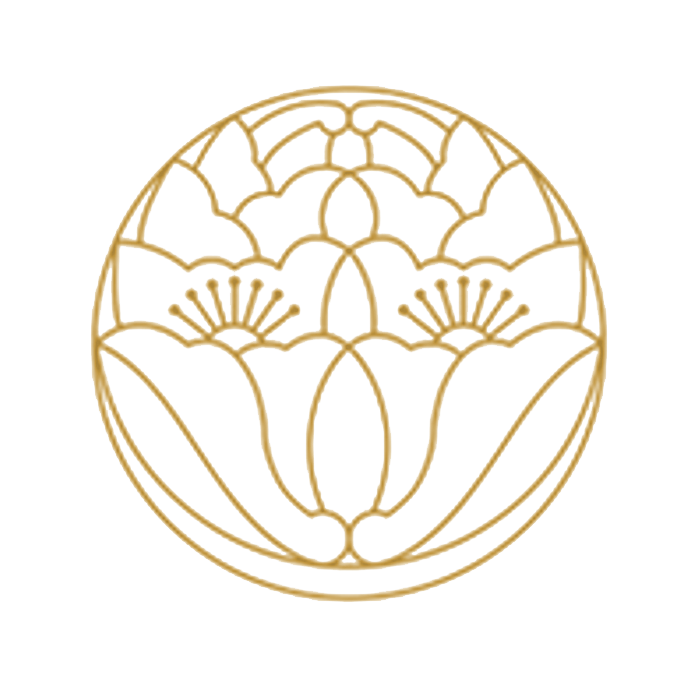「明遍」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
Seishimaru (トーク | 投稿記録) 細 (1版 をインポートしました) |
Seishimaru (トーク | 投稿記録) |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
康治元年(一一四二)—貞応三年(一二二四)六月一六日。入仏、[[空阿弥陀仏]]と号した。平安時代後期から鎌倉時代初期の僧。父は[[藤原通憲]](信西[[入道]])。兄弟に醍醐寺[[座主]]勝憲、<ruby>[[安居院]]<rt>あぐい</rt></ruby>[[澄憲]]、[[遊蓮房]]らがいる。はじめ[[東大寺]]で三論を叔父の敏覚と成宝に、覚海に[[真言]]中院流を学ぶ。平治の乱により佐渡に流されるが許されて嘉応二年(一一七〇)[[興福寺]]維摩会の[[講師]]を務め、承安二年(一一七二)には権[[律師]][[法橋]]の僧綱位を得ている。『[[四十八巻伝]]』によると、文治二年(一一八六)の[[大原問答]]に[[重源]]、[[貞慶]]らと共に列したと伝えられる。建久年間(一一九〇—一一九九)には[[律師]]の職を辞し、[[高野山]][[蓮華]]谷に[[隠遁]]したものと考えられる。[[東大寺]]大[[勧進]][[重源]]や[[仏師]][[快慶]]とも親しく、大阪・八葉[[蓮華寺]][[阿弥陀如来]]像、建仁元年(一二〇一)の奈良・[[東大寺]]僧形八幡神像、同安倍文殊院文殊五尊像(いずれも[[快慶]]作)に[[結縁]]している。 | 康治元年(一一四二)—貞応三年(一二二四)六月一六日。入仏、[[空阿弥陀仏]]と号した。平安時代後期から鎌倉時代初期の僧。父は[[藤原通憲]](信西[[入道]])。兄弟に醍醐寺[[座主]]勝憲、<ruby>[[安居院]]<rt>あぐい</rt></ruby>[[澄憲]]、[[遊蓮房]]らがいる。はじめ[[東大寺]]で三論を叔父の敏覚と成宝に、覚海に[[真言]]中院流を学ぶ。平治の乱により佐渡に流されるが許されて嘉応二年(一一七〇)[[興福寺]]維摩会の[[講師]]を務め、承安二年(一一七二)には権[[律師]][[法橋]]の僧綱位を得ている。『[[四十八巻伝]]』によると、文治二年(一一八六)の[[大原問答]]に[[重源]]、[[貞慶]]らと共に列したと伝えられる。建久年間(一一九〇—一一九九)には[[律師]]の職を辞し、[[高野山]][[蓮華]]谷に[[隠遁]]したものと考えられる。[[東大寺]]大[[勧進]][[重源]]や[[仏師]][[快慶]]とも親しく、大阪・八葉[[蓮華寺]][[阿弥陀如来]]像、建仁元年(一二〇一)の奈良・[[東大寺]]僧形八幡神像、同安倍文殊院文殊五尊像(いずれも[[快慶]]作)に[[結縁]]している。 | ||
---- | ---- | ||
| − | + | 【資料】『四十八巻伝』一六(聖典六) | |
---- | ---- | ||
【参考】名畑応順「明遍僧都の研究」(『仏教研究』一—三、一九二〇) | 【参考】名畑応順「明遍僧都の研究」(『仏教研究』一—三、一九二〇) | ||
---- | ---- | ||
【執筆者:青木淳】 | 【執筆者:青木淳】 | ||
2025年7月11日 (金) 06:39時点における最新版
みょうへん/明遍
康治元年(一一四二)—貞応三年(一二二四)六月一六日。入仏、空阿弥陀仏と号した。平安時代後期から鎌倉時代初期の僧。父は藤原通憲(信西入道)。兄弟に醍醐寺座主勝憲、安居院澄憲、遊蓮房らがいる。はじめ東大寺で三論を叔父の敏覚と成宝に、覚海に真言中院流を学ぶ。平治の乱により佐渡に流されるが許されて嘉応二年(一一七〇)興福寺維摩会の講師を務め、承安二年(一一七二)には権律師法橋の僧綱位を得ている。『四十八巻伝』によると、文治二年(一一八六)の大原問答に重源、貞慶らと共に列したと伝えられる。建久年間(一一九〇—一一九九)には律師の職を辞し、高野山蓮華谷に隠遁したものと考えられる。東大寺大勧進重源や仏師快慶とも親しく、大阪・八葉蓮華寺阿弥陀如来像、建仁元年(一二〇一)の奈良・東大寺僧形八幡神像、同安倍文殊院文殊五尊像(いずれも快慶作)に結縁している。
【資料】『四十八巻伝』一六(聖典六)
【参考】名畑応順「明遍僧都の研究」(『仏教研究』一—三、一九二〇)
【執筆者:青木淳】