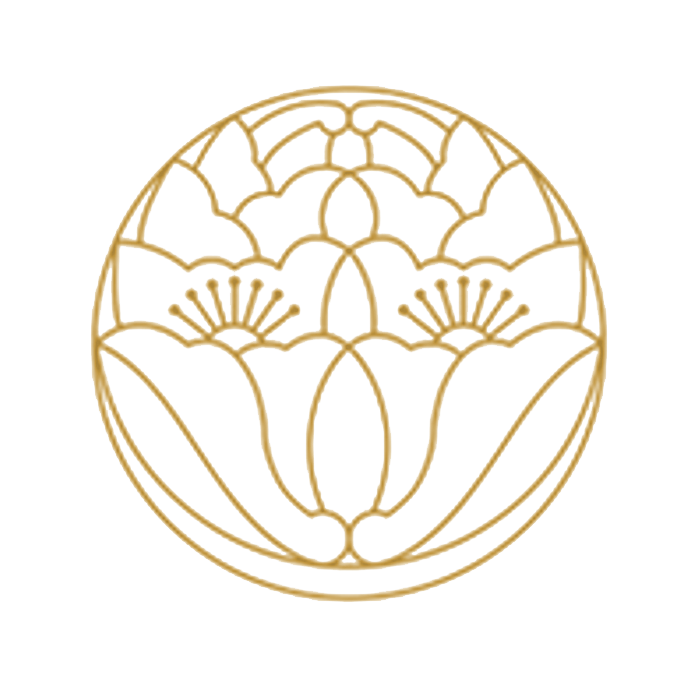古本漢語灯録
提供: 新纂浄土宗大辞典
2018年3月30日 (金) 06:23時点における192.168.11.48 (トーク)による版
こほんかんごとうろく/古本漢語灯録
一〇巻。義山による開版以前の古態をとどめた系統の『漢語灯録』のこと。道光の編集になる『黒谷上人語灯録』一八巻(『和語灯録』と『漢語灯録』で構成)は、浄土宗の義山によって開版され江戸・明治時代に流布したが、鎌倉時代の日本漢文を整った漢文体に改め、文章を付加削除して刊行された。一方、真宗大谷派の光遠院恵空が元禄年間(一六八八—一七〇四)に書写した『漢語灯録』一〇巻は、古態をとどめ道光編集時に近いとされる。浄土真宗本願寺派の玄智景耀は『浄土真宗教典誌』で、恵空本を古本、義山刊行本を新本と称し、それ以来、恵空本系統を古本『漢語灯録』と呼び習わしている。恵空自筆本は高倉学寮の火災で失われたようだが、江戸時代後期の転写本がいくつか残り、そのうち今岡達音が大正六年(一九一七)古書店で入手した善照寺本が学界に紹介され、その重要性が認知された。大谷大学にも東本願寺枳殻邸から移管された一本が所蔵され、この二本が古本の代表的写本である。このほかの転写本は調査報告が十分でない。古本の出現で研究が促進され義山版依用からの脱却が進み、昭和三〇年(一九五五)の石井教道編『昭法全』では底本に古本が多く採用された。古本の巻七・一〇の奥書によると、義山は「和州三輪之本」を書写し、のち「二尊院之蔵本」によって校合し、恵空はその校合の付された本を書写している。『恵空老師行状』には、二尊院本を発見したのは恵空で、彼がその流布を義山に慫慂したところ承諾したという。また巻八奥書には、道光生存中の嘉元四年(一三〇六)に「蓮花堂正本」を覚唱が写したという早い時期の流伝を伝え、その後も中世に転写を重ねている。奥書の三光院や来迎寺は奈良の西山派寺院である。平成七年(一九九五)に発見された大徳寺本『拾遺漢語灯録』は古本系で、これで古態をとどめた『漢語灯録』が揃ったことになる。
【資料】仏教古典叢書『古本漢語灯録』(中外出版、一九二四、再刊一九八四)、浄土宗総合研究所編『黒谷上人語灯録写本集成1 善照寺本古本漢語灯録』(浄土宗、二〇一一)
【参考】藤原猶雪『日本仏教史研究』(大東出版社、一九三八)、宇高良哲『逆修説法諸本の研究』(文化書院、一九八八)、中野正明『法然遺文の基礎的研究』(法蔵館、一九九四)、善裕昭「古本漢語灯録の奥書について」(『現代社会と法然浄土教』山喜房仏書林、二〇一三)
【執筆者:善裕昭】