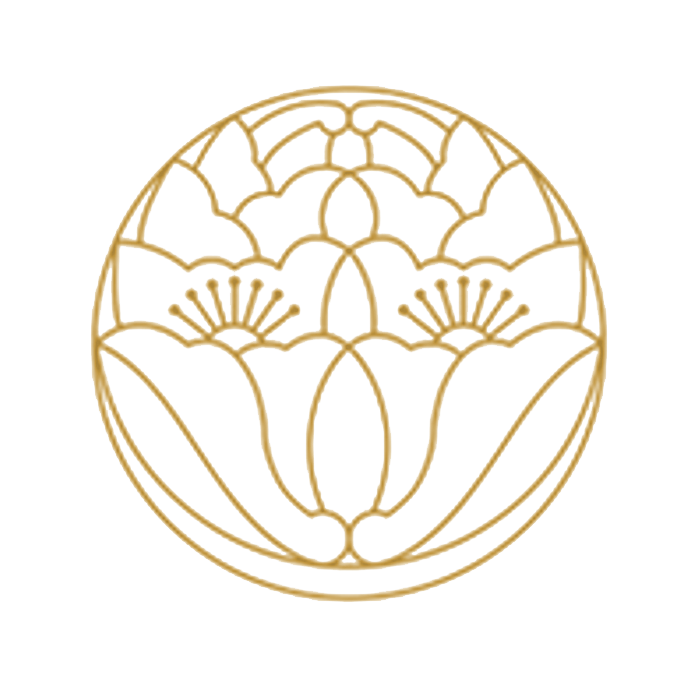十王
提供: 新纂浄土宗大辞典
じゅうおう/十王
『預修十王生七経』などに説かれる一〇人の裁判官のこと。秦広王・初江王・宋帝王・五官王・閻魔王・変成王・泰(太)山王・平等王・都市王・五道転輪王の一〇人。人が亡くなった後、七日ごと、あるいは一〇〇日目、一年目、二年目にそれぞれ王によって裁かれる。なかでも三五日目の閻魔王の裁判は有名。いわゆる中陰の追善供養などは、これらの裁判で少しでも罪が軽くなるよう行われる。中陰(中有)の思想はインドにもあるが、十王による裁判については中国で考え出されたもので、『預修十王生七経』に「成都府大聖慈寺沙門蔵川述」と記されてあることからも分かるように、中国で作られた偽経である。十王中、インド撰述の経典に出てくるのは、閻魔王と転輪王だけで、他のものは中国の道教などの影響を受けて生み出されたものと考えられる。ただし、閻魔王(閻羅王)については、『長阿含経』地獄品に亡者(罪人)の裁判を行うことが説かれている。なお、それぞれの王は、本来、如来や菩薩が裁判のため王という仮の姿に身を変えているとされる。これらは中国の十王思想を受けて平安時代に日本で形作られた『地蔵菩薩発心因縁十王経』という偽経に説かれたものとされてきたが、近年その説に対し疑義が唱えられている。以下、本経(続蔵版)が説く裁判の日と本地としての仏・菩薩名を記しておくが、宗派などによって多少内容が異なる。 初七日(七日目) 秦広王(不動明王)
二七日(一四日目) 初江王(釈迦如来)
三七日(二一日目) 宋帝王(文殊菩薩)
四七日(二八日目) 五官王(普賢菩薩)
五七日(三五日目) 閻魔王(地蔵菩薩)
六七日(四二日目) 変成王(弥勒菩薩)
七七日(四九日目) 太山王(薬師如来)
百箇日(一〇〇日目)平等王(観世音菩薩) 一周忌(一年目) 都市王(阿閦如来)
【参照項目】➡十三仏
【執筆者:横田善教】