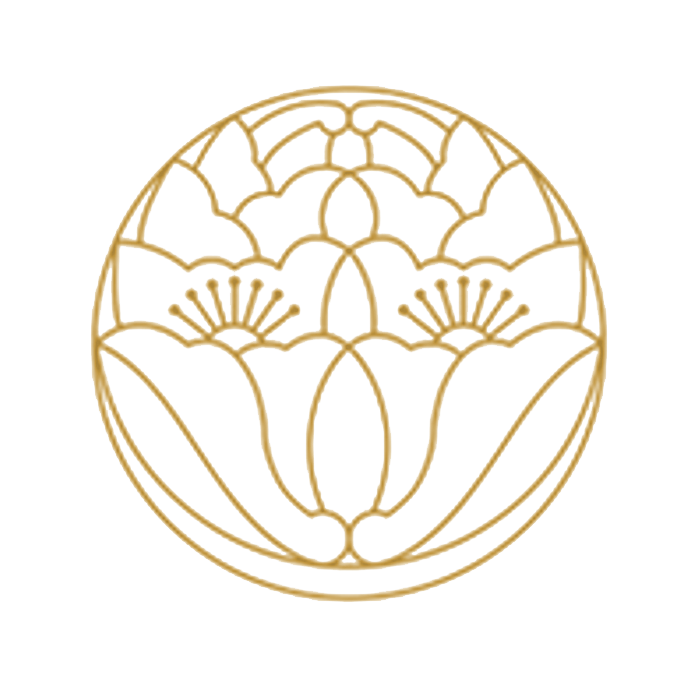宗教経験
提供: 新纂浄土宗大辞典
しゅうきょうけいけん/宗教経験
人びとの宗教生活の過程でおこる、とくに強烈な集中・充実や高揚感などを伴う独特の経験のことで、宗教の主要な要素の一つと考えられる。個人的・情意的なニュアンスを強調するときには「宗教体験」ともいう。宗教経験の後、一定の時間が経つとふたたび日常の生活リズムに戻るのが通常であるが、単に一過的ではなく、当事者の人格に何らかの永続的な刻印を残し、以後の行動を決定的に方向づける。この点で真正の宗教経験は、しばしば類比されるLSDなど、薬剤のもたらす効果とは明らかに区別されるべきである。宗教経験の可能性は、原則として万人に開かれたものであるけれども、実際には、それは教祖・預言者・神秘家・聖人など、優れた宗教家たち個人の事例に即して語られることが多い。彼らの宗教的な生涯の転機をなした回心(入信)・召命、あるいは神秘体験(合一・見性など)が、その典型とみなされるためである。法然四三歳の専修念仏への帰依や三昧発得もここに数えられる。こうした経験は、当事者にとって、意図したものでなくむしろ自らを超える外部の力によって、しかも突如もたらされたとしばしば感じられる。しかし、近代における宗教心理研究は、この種の転換には常にそれに先立つ一連の準備段階があり、時にはそこに鋭い「内観」が働いていることを明らかにした。例えば古代インドなど、高度の文明を背景とした宗教では、その内観がさらに展開・整理され、洗練された修行の技法が生みだされた。このヨーガ(瑜伽)の伝統が仏教の基本としての禅定行につながることは言うまでもない。このように、非日常的な宗教経験が実は日常的な「行」と不可分であることは、それを育む歴史的・集団的な背景の影響とともに、看過してはならない重要な点である。
【参考】W・ジェイムズ著/桝田啓三郎訳『宗教的経験の諸相』(岩波書店、一九七〇)、島薗進・西平直編『宗教心理の研究』(東京大学出版会、二〇〇一)
【執筆者:田丸徳善】